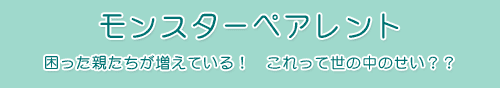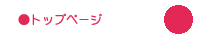
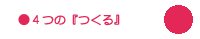

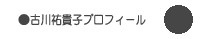
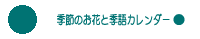
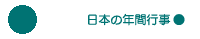  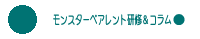

●こどもと親のためのお役立ちリンク
●お問い合わせ・講演依頼
|
●2人の子どもが、ささいなことでけんかに。担任に「2度と同じクラスにするな」と言い寄ったようです。(モンスターペアレントの事例 サンケイリビング 2008年3月15日号より)
●小学校で、「子どもにケータイを持たせたい。なぜだめなのか?」と先生に詰め寄った保護者がいたそうです。(モンスターペアレントの事例 サンケイリビング 2008年3月15日号より)
●運動会のリレー選手をじゃんけんで決めたのに「自分の子が負けたから」と言って、担任にやり直しを要求。(モンスターペアレントの事例 サンケイリビング 2008年3月15日号より)
●土曜日に開催される予定だった運動会。2週間前になって、「その日は仕事なので、日曜日に変えてください」と言いに行った保護者が。それに対して先生は、「年間行事で決まっていることで知らせているし、変更はできません」と伝えていました。(モンスターペアレントの事例 サンケイリビング 2008年3月15日号より)
●クラスで集合写真をとったときのことです。出来上がった写真をみて、「うちの子が真ん中に写っていない」と言った人が。担任の先生は、「写真は、誰かが端になるので仕方ないんです・・・」と根気よく話していました。(モンスターペアレントの事例 サンケイリビング 2008年3月15日号より)
|
| 対策として、研修でグループ討議 |
神戸市教育委員会では、各校での職員研修や、教育委員会で実施する研修の中で、短縮事例研修を行っています。「コミュニケーション力を養い、保護者との連携をより強化するために行うものです」(指導課生徒指導係)。この研修では、架空の事例をもとに、登場する教師の言動や指導方法について、適切ではないと思われる部分を、一人ひとりが見つけ出し、グループ討議で、よりよい対応のあり方や、指導方法について協議します。
(モンスターペアレントの事例 サンケイリビング 2008年3月15日号より)
|
| 先生にも“聴く力”が必要 |
「保護者にも先生にも必要となってくるのは、“聴く力”」と言うのは、消費者のクレームについて研究を行っている関西大学社会学部・准教授の池内裕美さん。「言う側も聞く側もコミュニケーション能力が必要となってきますし、『相手が本当は何を求めているのか?』、本質をしっかり聴きとることが重要になりますね。」
(モンスターペアレントの事例 サンケイリビング 2008年3月15日号より)
|
運動会が雨だったのは「校長が雨男のせい」という抗議をする保護者もいる!
雨男の根拠は?ある意味ギャグかなと思ったのですがいやはや校長も大変ですね。
(朝日新聞の記事より)
| ☆その他実例 |
○飲食店で走り回って騒ぐ子どもにやんわり注意した店員が[なぜ子どもに注意する]と逆キレした親に抗議され泣いてしまった
○スーパーで豆腐をつついて穴を開けている子どもに注意したら、母親が[何であんたに言われる筋合いがあるの!買えばいいんでしょ]と啖呵を切られた
○満員の飲食店。順番待ちの席の前が空いているのにつめないので「前につめてもらえませんか?」というとにらみつけられ「私に注意した」と逆キレ(他の人は立っているにもかかわらず)
この実例おかしいと思いませんか?
電車の中で騒いでいる子どもに[周りの人に迷惑だからやめなさい]としつける親は少ないなあと感じます。
よくある[あのおじさんがにらんでいるよ]という言い方。
他人に責任を転嫁していませんか?
では人が見ていなければ何をしてもいいのか。ということになります。
|
| ☆教職員編 |
○学校の廊下ですれちがう時に、こちらが会釈やあいさつしてもあいさつしない
○保護者に敬語を使わない教師
○一方的に意見をいってこちらの言い分を聞かない
保護者がモンスターペアレントになるのはお互いのコミュニケーション不足もあると思うのです。親と教職員の誤解が大きな問題に発展していくのではないでしょうか?
相手が何を「いいたいのか」を理解し、その上で「わたしはこう思う」という意見を感情的にならずに伝えられたらもっと建設的な関係が築けるのです。
日本人特有の自己主張や意見を言うのを遠慮してしまう。上手く伝えられないもやもやがたまって爆発してしまう!ということもありますね。
|
そこで「教職員のコミュニケーションセミナー」をぜひお受け下さい
ロールプレイングの実践中心に[身に付くセミナー]です。
教職員マナーセミナー
教職員と保護者のコミュニケーション向上トレーニング
啓蒙小冊子やマニュアルも作成いたします
○モンスターペアレントQ&A
○保護者との良い関係を築く話しかた
|
|
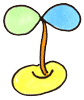


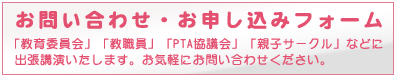
![こころをつくる[講演・研修]](bt_main-cocoro.gif)
![つながりをつくる[地域活性化プロジェクト]](bt_main-tsunagari.gif)
![からだをつくる[食育・礼儀etc]](bt_main-karada.gif)
![おもいでをつくる[イベント・行事体験]](bt_main-omoide.gif)